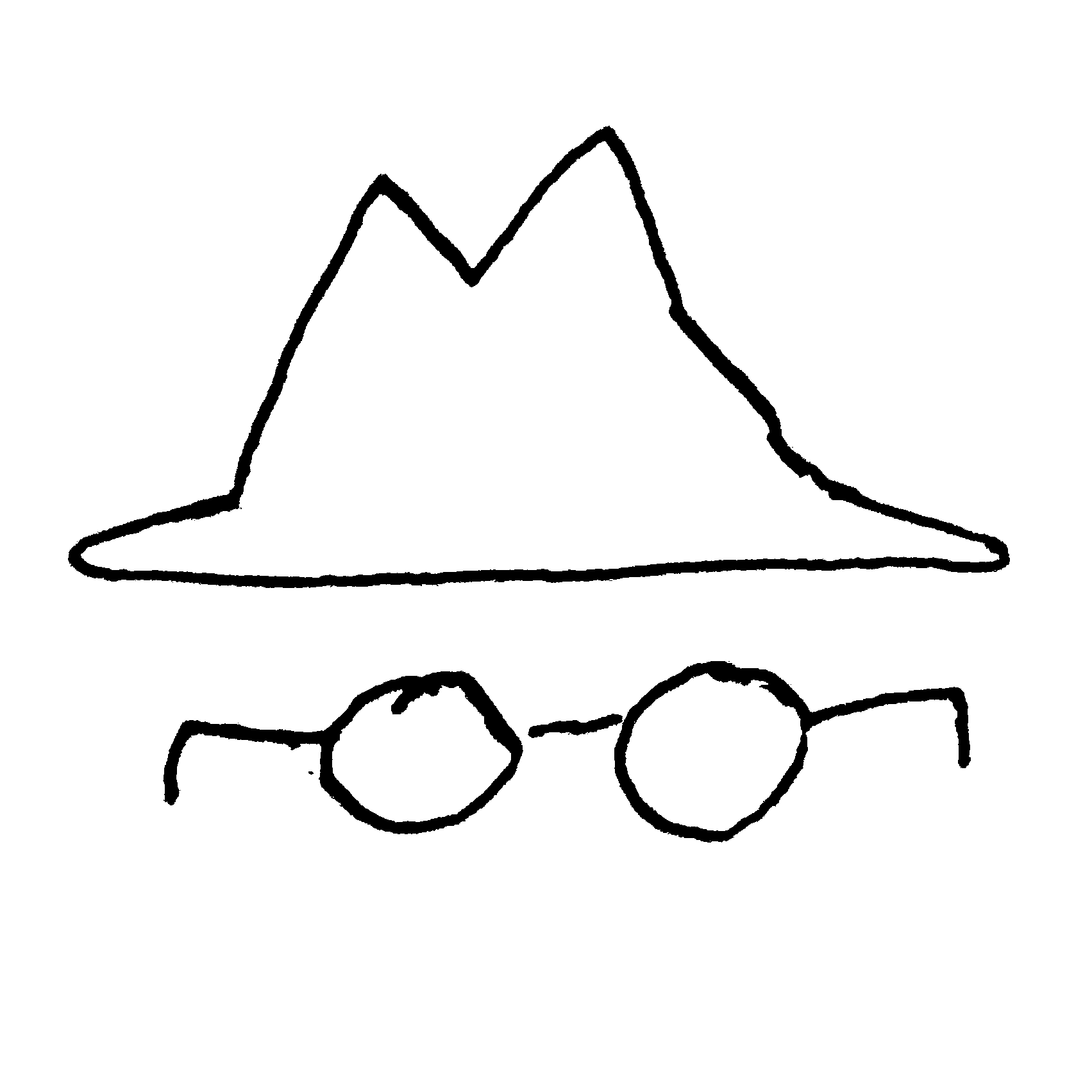シュワッと爽快な音のウラにある、クラフトビール市場の「熱狂」と「ストーリー」
さまざまな個性で人を魅了するクラフトビール
皆さんの旅行の楽しみといえば、豊かな景色でしょうか、素敵な建築物でしょうか、いいえ私はビールです。地方ごとに、見た目でも味わいでも、楽しみを与えてくれるクラフトビールが旅先での密かな楽しみのひとつという方も多いのではないでしょうか。
日本のクラフトビール市場は、今まさに熱狂の渦中にあります。ある調査によれば、その市場規模は2024年時点で約1兆2000億円に達し、2033年に向けて年平均12%以上という大きな成長が予測されています。
しかし、この熱狂の裏側で、静かに「淘汰の波」が迫っているとしたらどうでしょうか?
ブランディングの目線から、クラフトビール市場の動きを探ってみましょう。
クラフトビールはいったい何をクラフトしているのか?
クラフトビールの魅力は、画一的な味わいの大手ビールにはない、その「多様性」と「物語性」にあります。
例えば、広島の尾道を拠点とする「しまなみブルワリー」は「ラガースタイルの追求」を掲げ、最高の一杯を目指す一方で、地元尾道のレモンを使ったレモンサワー商品を開発するなど、地域に根差したストーリーをつむいでいます。
また、福岡にある「青空ブルワリー」は、都心部にありながら、店内に醸造所とタップルーム(バー)を併設する「ブルーパブ」となっています。ここでは、タンクから注がれたばかりの新鮮なビールを味わうことができます。これは単なる飲食ではなく、「造り手とつながる」「その場でしか得られない」という特別な体験価値を提供しています。
彼らは単に「美味しいビール」を売っているだけではありません。デザインや体験を通じて、独自の「物語」と「存在価値」を私たちに届けているのです。
クラフトビールにもホロ苦い時代がありました
そもそも「クラフトビール」とは何でしょうか。明確な定義はありませんが、一般的に「小規模な醸造所(マイクロブリュワリー)が、職人技を駆使して造る、多様で個性的なビール」とされています。日本でクラフトビールが花開いた背景には、1994年の酒税法改正があります。
これにより、ビールの年間の最低製造量が引き下げられ、マイクロブルワリーの設立が容易になりました。この規制緩和が、市場の熱狂の出発点となりました。この流れをつかみ、大きな成功を収めたのが「よなよなエール」で知られるヤッホーブルーイングです。
1996年に星野リゾートの創業の地、軽井沢で初声をあげ、「地ビール文化の開花」「そこでしか飲めないユニークなビールの提供」という思いで星野リゾートにより立ち上げられました。
しかし、参入障壁が下がったことで、競争が激化しました。ブームに乗っかっただけの醸造所が乱立し、消費者の間では「地ビール=不味い、高い、モノ珍しいだけ」というネガティブなイメージが定着してしまい、ブームは急速にしぼんでいきました。業界の巨人、ヤッホーブルーイングでさえ、地ビールブームの沈静化とともに、一時期は苦境に陥ったのです。
現在は、ビールづくりのノウハウも流通し、美味しいビールをつくるブルワリーが増え、今や「美味しい」は当たり前の基準になりました。それだからこそ、憧れだけで参入しても、ファンをつかみ、事業を継続していくことは容易ではない状況ともいえます。
クラフトビール大国アメリカが示す現実とは
この「美味しいだけでは勝てない」という現実は、クラフトビール大国・アメリカの市場が先行して示しています。
アメリカでは、1970年代初頭から長年のブームを経て市場が成熟。ポートランド(オレゴン州)やサンディエゴ(カリフォルニア州)などを中心に多様なビアスタイルが定着していきました。ブルワリーの数は1万件に迫る勢いでしたが、2020年頃からついに、年間の「閉業数」が「開業数」を上回るという、サバイバルの時代に突入しました。

消費者は無数の選択肢を前にし、本当に価値を感じるビール、自分が共感できるブランドしか選ばなくなっているということではないでしょうか。
これは、決して対岸の火事ではありません。成長市場である日本も、いずれは同じ道をたどる可能性も高いでしょう。多様性が飽和状態となったとき、消費者は何を基準にビールを選ぶのでしょうか?
クラフトビールはカルチャーをまとい、生き残りの道を探した
味が良いのは当たり前。品質が良いのも当たり前。そんな飽和した市場で、顧客に選ばれ、愛され続けるために、クラフトビールはカルチャーとマッチする道を選びました。
味という形のないものを表現するために、タレントを起用した大規模なPRが難しいマイクロブリュワリーにとって、特定のカルチャーと深く融合し、独自のポジションを確立していくのは必然だったと言えます。
うちゅうブルーイング
醸造家とクリエイティブディレクターのコンビにより生まれた山梨県発のマイクロブルワリー。独自栽培のホップを使用し、フレッシュなホップの味わいと環境に負荷をかけないビール造りを両立しています。パッケージのサイケデリックさや、「宇宙QUEST」など独特のネーミングが、不思議な魅力を持っています。ECサイトでの販売分は即完売するなどの人気ぶりです。
Teenage Brewing
創業者である森大地氏の音楽家としての背景と、「ティーンエイジ」という名前に込められた哲学が色濃く反映されているブリュワリーです。楽曲づくりのように、様々な要素を重ね合わせ、感性でつくるビールが印象的で、「ティーンエイジ」のように挑戦的でありたいという願いも込められています。スッキリとしたピルスナーやペールエールはもちろん、サワービールや木を使ったビールなど振り切った個性のある刺激的なビールも作っています。

CRAFTROCK BREWING
東京・高円寺のCRAFTROCK BREWINGは「音楽とクラフトビールの融合」を体現するブランドです。このブルワリーパブはライブハウスを併設しており、出来立てのビールを片手にライブを楽しめるという、音楽好き・ビール好きには夢のような空間を提供しています。さらに、音楽フェスティバル「CRAFTROCK FESTIVAL」を主催し、日本のクラフトビール×音楽カルチャーの最前線を走っています。
BrewDog
そして、スコットランド発のBrewDogの事例は有名です。彼らは自らを「PUNK(反骨)」と定義し、過激なマーケティングで社会に異議を唱える「ムーブメント」としてのブランドを確立しました。ロンドンを戦車で走行し、巨大な金融システムへ「反逆」をアピールするなど、その姿勢は徹底しています。人々は彼らのビールを飲むことで、その思想や世界観の共犯者となるのです。結果、従来のビールでは物足りなさを感じていた世界中のビアギークを虜にしています。かくいう私も、その企みにまんまと乗り、ビアバーで同社の「PUNK IPA」をよく飲んでいました。
クラフトビールのストーリーをいただこう
味が飽和したクラフトビール業界が教えてくれるのは、「どんな人に、どんな気分で楽しんでもらい、その人にとってどんな存在になりたいか」という、明確なポジションを築くことの重要性ではないでしょうか。
共感やストーリーなど、目に見えないモノを適切なファンに届け勝負をしていくことです。あなたにも思い当たることがありませんか、あなたがモノを選ぶとき、味や機能ではなく自分の好きに耳を傾けて選択をしている。そこに、ストーリーがあるからではないでしょうか。あなたの身の回りにあるブランド、それはあなたという人の代弁者ではないでしょうか。
今度、ビールを選ぶときは、味だけでなく、「行ってみたい国」「社会活動への共感」「弾けるようなデザイン」「醸造に至るまでのストーリー」など、自分が本当に好きなもの、ずっと付き合っていきたいブランドを探してみてはどうでしょうか。
ほら、タブをプシュッと開けると醸造家たちの、誇りや喜びが聞こえてくる…気がしませんか。と、難しいことは一杯目までにして、何も考えずにただ楽しく二杯目をいただくのも、クラフトビールへの最高の恩返しの一つに違いありません。